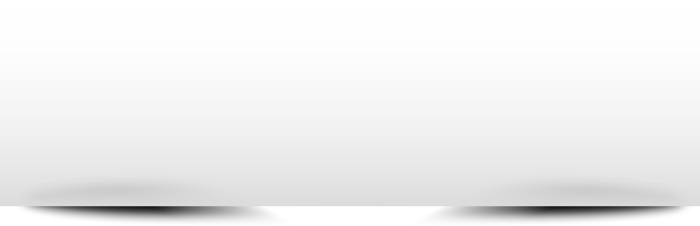岐阜県 揖斐郡 池田町 建設会社 建築会社 工務店 仏閣工事 本堂工事 改修工事 リフォーム工事 新築工事

http://ksouken.jp/
モバイル版はこちら!!
バーコードリーダーで読み取り
モバイルサイトにアクセス!
モバイル版はこちら!!
バーコードリーダーで読み取り
モバイルサイトにアクセス!
株式会社河村綜建
〒503-2422
岐阜県揖斐郡池田町田畑699-3
フリーダイヤル.0120-704-183
TEL.0585-45-5935![]()
FAX.0585-45-5418
●主な業務内容
1.総合建設業
2.分譲住宅
3.土木工事
4.神社仏閣
●業務上の免許・資格
・一級建築士
・一級土木施工管理技士
・宅地建物取引
・一級建築施工管理技士
・構造一級建築士
・設備一級建築士
----------------------------------
夢ハウス・のぞみ株式会社
〒503-2422
岐阜県揖斐郡池田町田畑699-3
TEL.0585-45-5983![]()
FAX.0585-45-5983
●主な業務内容
1.不動産業
●業務上の免許・資格
・宅地建物取引
037070
<<株式会社河村綜建>> 〒503-2422 岐阜県揖斐郡池田町田畑699-3 TEL:0585-45-5935 FAX:0585-45-5418
Copyright © 株式会社河村綜建. All Rights Reserved.